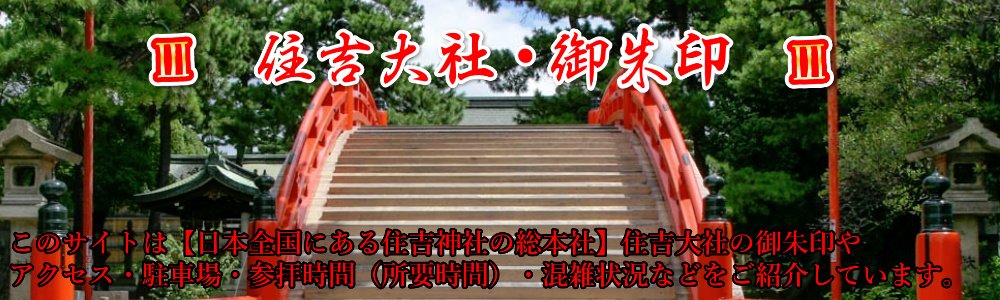露天神社は「お初天神」の名前で、大阪人に親しまれています。
神社と言えば人気のない静かな場所に佇むイメージですが、露天神社は大都会の喧騒の中にある神社です。神社に訪れるのは千鳥足のサラリーマンや、キタに遊びに来た若い人の姿も珍しくありません。
何度訪れても飽きない、露天神社の見どころをご紹介しましょう。
露天神社(お初天神)の簡単な歴史・由緒
1000年以上前のキタ界隈は、小島だらけの場所でした。キ
タ界隈にあった小島の1つが、「曽根洲(そねしま)」です。
曽根洲に住吉須牟地曽根ノ神(すみよしすむちそねのかみ)が祀られたのが、露天神社の始まりと言われております。
難波八十島(なにわやそしま)祭り
住吉須牟地曽根ノ神が祀られていた場所は、「難波八十島祭」で使われてきました。
「難波八十島祭」とは、天皇が即位する際に執り行われる儀式のことです。
キタ界隈にある小島を新たに天皇になる人物が自ら回り、島にいる神様から祝福を受けるというものだったそうです。
難波八十島祭は、平安時代~鎌倉時代まで執り行われました。
島から都市へ
島から都市になったのは、南北朝時代に入ってからのこと。
豪族である渡辺氏が曽根崎に移り住み、土地開発に取り組みました。
そして曽根崎一体を守護してもらうために、曽根洲で祀られていた神様を「露天神社」として祀ることになったのです。
「露天神社」の名前の由来は菅原道真
「大阪グルメ激戦区」としてグルメな人から熱い注目を浴びる福島は、何の皮肉か昔は「飢餓島」と呼ばれていました。
飢餓島に赴いた人物こそが、菅原道真です。
目的は観光ではなく、京の都から九州へ左遷された際に立ち寄ったとされています。
飢餓島に立ち寄った際に、菅原道真は「露の散る涙に袖は朽ちにけり 都のことを思いつづれば」と一句詠み上げます。
太融寺に向かった折、草露が菅原道真の袖を濡らした時に詠まれた句です。
道真が詠み上げた句が、露天神社の名前の由来になったと言われています。
じゃあ「お初天神」の名前の由来って何?
露天神社の名前に由来はわかったのですが、じゃぁ「露天神社」の名前の由来って何??‥などという疑問が沸き起こりますが、お分かりになりますか?
1703年(元禄16年)のこと。
当神社の境内において「お初」という、ちょぃとワケありの女性が、なんと!奇しくも心中事件を起こしたそうです。
その後、このお初の話は有名になり、人形浄瑠璃の異才者「近松門左衛門」が、自身の名作として知られる「曽根崎心中」を書き上げたのです。
以来、「曽根崎心中」を観た人たちの間で「お初」のいた天神さまということで、「お初天神」という愛称が広まっていきます。お初天神の境内見どころ
拝殿と本殿
現在の露天神社の拝殿と本殿は、1964年(昭和32年)に建てられたものです。
後ろに本殿がございますが、場所的にめちゃくちゃ見えにくくなっています。
神社の歴史が1300年でありながら、拝殿が作られたのは昭和に入ってからのことでした。
拝殿と本殿は、これまでに3回消失したからです。1回目は大坂夏の陣・2回目は北の大火・3回目は第二次世界大戦時に消失しました。
大坂夏の陣と北の大火
大坂夏の陣は、1615年(慶長20年)に勃発。
戦いは熾烈を極め、大坂は一面火の海となりました。
露天神社も戦いに巻き込まれ、大炎上!拝殿や社殿は跡形もなく消えてしまいました。
北の大火は、曽根崎を始め梅田のほとんどを焼き尽くした大火事です。工場から出火した炎は、空気の乾燥により勢いを増しました。
十分な消火もできなかったため、甚大な被害をもたらすことになったのです。
第二次世界大戦
露天神社を襲った悲劇で最も酷いものは、第二次世界大戦時の大空襲でしょう。
万単位の罪なき人だけでなく、土地の守り神として崇められていた露天神社をも襲いました。
しかし一度や二度の焼失で、めげる大阪人ではございません。
大阪夏の陣や北の大火の時でも、見事に露天神社再建を果たしたのです。
もちろん第二次世界大戦時で崩れた露天神社も、地元氏子達の働きにより昭和32年に再建しました。
露天神社を襲った悲劇は過去のものとなり、今では観光客や千鳥足のサラリーマン達が集う場所となっております。
拝殿近くにあるのは心美人の手鏡
拝殿の壁にかけられているのは、心美人の手鏡。「外見の美しさは一時的なもの。
心の美しさは一生の宝物」という言葉を胸に、精進したいものです。
また露天神社は、美人絵馬も有名です。
絵馬に「なりたい理想の顔」を書いて願いを込めれば、べっぴんさんになれるかもしれません。
注連柱
拝殿前にあるのが注連柱です。注連柱の下には、虫食いのような穴があります。
穴は虫食いではなく、今から70年以上前大阪に襲来したグラマン戦闘機の機関銃弾痕です。
大阪大空襲を経験した古老の話によると、戦闘機は超低空飛行で一般人めがけて、機関銃を発射。
ある日突然戦闘機に追いかけられるのは、想像がつかないほどの恐怖だったに違いありません。
もう二度と、恐ろしい戦争が起きないことを心より祈るばかりです。
神牛舎
日本全国の天満宮(天神さん)に祀られているのが、神牛舎です。
「撫牛」とも呼ばれています。
天神さんに佇む牛は、悪い所を治してくれると信じられています。
例えば、頭痛が酷い場合は牛の頭を撫でてから自分の頭を撫でると、牛が頭痛を治してくれるというものです。
玉津稲荷(開運稲荷社)
- 御祭神:玉津大神・天信大神・融通大神・磯島大神
- ご利益:商売繁盛・五穀豊穣・皮膚病治癒
拝殿左手側にあるのが、開運稲荷社です。
奥まった所にあるので見つけづらいかもしれませんが。
朱色の鳥居で出来たトンネルを目印に探してみて下さい。
元々は、露天神社付近に祀られていた4社の稲荷社でした。しかし1909年(明治42年)に起きた北の大火により、4社の稲荷社は焼失。翌年1910年(明治43年)焼失した4社を合祀したのが、開運稲荷社(玉津稲荷)です。
一昔前、開運稲荷社には皮膚病が治るようにと「なまず」の絵馬が多く架けられていたそうです。
なぜナマズかについてですが、玉津稲荷の「たまつ」が「なまづ」と訛ったからと思われます。
またナマズにはビタミンAの一種であるレチノールが含まれており、肌を生まれ変わらせる効果がございます。
昔の方は「ナマズを食べたらお肌がスベスベになったから、ナマズは皮膚病のご利益がある神様だ」と、考えたのかもしれません。
曽根崎心中の舞台になった場所
露天神社(お初天神)を語る上で欠かせないのが「曽根崎心中」でしょう。
誰よりも強く愛し合った2人の物語は、心中事件から300年以上経った現代の人の心も掴んでおります。
曽根崎心中の舞台になったことから恋愛成就のご利益があると話題になり、毎日のように恋に悩む人が訪れる場所となりました。
曽根崎心中の大まかなあらすじ(完全ネタバレ)
醤油屋の手代(しゅだい・今で例えたら中間管理職のようなもの)である徳兵衛には、お初という恋人がいました。
元々2人は相思相愛の関係でしたが、しばらく会わずにいました。
ある日のこと、2人は偶然にも生玉神社(いくたまじんじゃ・現在の生國魂神社)で再会を果たします。
お初と再会してすぐ、徳兵衛に結婚の話が舞い込みました。
相手は醤油屋の店主の姪で、結ばれれば大出世です。
しかし徳兵衛にはお初がいたため、結婚話を断ります。
店主が持ちかけた結婚話を断ってからの徳兵衛には、様々な試練が訪れました。
試練を乗り越えるには、自らの命を絶つしかない状況にまで追い込まれます。
どうせ最期になるからと、心から愛するお初の元に駆け寄る徳兵衛。
お初は徳兵衛の覚悟を聞き、共に果てることを決心しました。
2人は共に手を取り、曽根崎の森にある露天神へと向かいます。
露天神社にて徳兵衛はお初を手にかけ、徳兵衛は自らの手で生涯を終えました。
お初と徳兵衛ゆかりの地像
2人が共に果てたとされる場所にあるのが、お初と徳兵衛ゆかりの地像です。
心中事件が起きてから、301年後の2004年(平成16年)に建てられました。
像のモデルになったのは、二代目中村鴈治郎と中村扇若(現:四代目坂田藤十郎)です。
曽根崎心中は、1953年(昭和28年)に東京にある新橋演舞場で公演されました。
当時の舞台写真を元につくられたのが、お初と徳兵衛ゆかりの地像です。
除幕式には、お初像のモデルになった四代目坂田藤十郎とご長男の四代目中村鴈治郎が出席しました。
難転石
開運稲荷社の参道近く・お初と徳兵衛ゆかりの地像の前にあるのが、難点石です。
「福」と刻まれている大きな石を回すことにより、厄除けのご利益が授けられます。
お願い方法は、男性は左・女性は右へ回して幸せを祈りましょう。
なお難点石の由来は、石を回すことで災“難“から”転“じて幸せになることから名付けられました。
恋人の聖地
かつてお初と徳兵衛が愛を貫いた場所は、今では「恋人の聖地」になりました。
「恋人の聖地」とは、NPO法人が定めたプロポーズにおすすめの場所として認定された場所を指します。
選定委員には、世界的なブライダルファッションデザイナー・桂由美の姿もあり、その道の”プロ”が勤めております。
プロポーズの場として選ばれたのが、露天神社です。
お初と徳兵衛が最期の最期まで愛を貫いたとして、プロポーズにおすすめの場所として選ばれました!
水天宮と金刀比羅宮
- 御祭神:天乃御中主大神、安徳天皇、大物主大神、崇徳天皇、住吉大神、他二柱(御祭神)
- ご利益:安産、児童守護、交通安全、水関係職種の守護
水天宮は、1797年(寛政9年)に、久留米藩(現在の福岡県久留米市)蔵屋敷内で祀られた社でした。
かし明治維新の際に久留米藩の蔵屋敷は朝廷に返されることになったため、丸亀藩(現在の香川県丸亀市)の蔵屋敷にあった金比羅宮と合祀されることになります。
その後、丸亀藩の蔵屋敷も朝廷に返されることになったため、高松藩(現在の神奈川県高松市)の蔵屋敷に預けられることになりました。
そして水天宮と金比羅宮は、堂島中2丁目あたりに祀られることになります。
やっと落ち着いたと思った矢先に、今度は北の大火が発生。水天宮と金比羅宮は被災してしまいました。
そして2つの社は、露天神社の境内社で一緒に祀られることになったのです。
蔵屋敷の神様
水天宮 金比羅宮が渡り歩いた久留米藩の蔵屋敷・丸亀藩の蔵屋敷・高松藩の蔵屋敷は、全て大阪の堂島あたりにあった蔵屋敷です。
大阪に蔵屋敷が集中していた理由は、「大阪は天下の台所」の一言で説明がつきます。
大阪は日本のほぼ真ん中に位置し、陸路や水路が発達していたことから、物流の一大拠点となっていました。
取引されていた商品の中で、最も重要な役割を果たしたのが米です。
米を日本全国に流通させるための倉庫だったのが、各藩の蔵屋敷になります。
蔵屋敷は米倉庫の他にも、藩大名達のホテルや幕府の情報を得るための窓口にも使われました。
安産祈願
孝明天皇が安産祈願をされた場所こそが、当時久留米藩の蔵屋敷に祀られていた水天宮です。
孝明天皇の安産祈願によって無事に生まれた子供は、後に明治天皇となる人物でございます。
江戸時代の頃、医学は現代のように発達はしておりません。
子供を一人人産むだけでも、命がけのことだったのです。例え皇族でも、できることは神頼みしかありません。
孝明天皇の安産祈願の話が伝わると、庶民の間でも「水天宮 金比羅宮には安産祈願のご利益がある」と広まるのは自然の流れと言えるでしょう。
安産祈願のご利益は効果絶大で、SNSでは「お初天神に参拝したら無事に赤ちゃんを授かることができた」や「参拝のおかげで安産になった」と、投稿されていました。
また安産祈願守りは大変な人気で、売り切れることも珍しくないそうです。
もし近々出産を控えているのなら、体調の良い時を見計らってお参りに訪れてみてはいかがでしょうか。
難波神明社/夕日の神明
- 御祭神:天照大神・豊受姫大神
- ご利益:五穀豊穣・商売繁盛・国家安泰
始まりは821年(弘仁12年)、当時のキタ界隈は今の様な繁華街ではなく、幾つもの島が点在しておりました。
点在していた島の1つ、現在の西天満辺りに祀られたのが難波神明社の始まりです。
難波神明社は、西向きに社が建っていることから別名「夕日の神明」と名付けられています。
東向きの社は此花区(USJがある所)の朝日神明社・南向きの社は大正区(京セラドームがある所)の神明神社、難波神明社と合わせて「大阪三神明」と呼ばれております。
難波神明社(夕日の神明)に訪れた人の中には、牛若丸でお馴染みの源義経の姿もありました。
かつて現在の大阪市福島区福島にあったと伝承される「逆櫓の松(さかろのまつ)」にて梶原景時と議論した際には神明社に社参し、寄進したと伝えられています。
江戸時代には大阪城代(役職の一種。大阪城を守るのが主な仕事)が、社参したそうだが、当時の難波神明社は境内が広々としており、界隈では名前の知れた観光スポットだったらしい。
しかし1834年(天保5年)に社殿が焼失し、1909年(明治42年)の北の大火が致命傷となり、以来、難波神明社は衰退の一途を辿ったが、翌年になると露天神社へ合祀され、現今に到る。
御井社(みいしゃ)・祓戸社(はらえどしゃ)
- 御祭神:御井神(みいのかみ・露ノ井とも呼ばれていた)・祓戸社四柱ノ神
- ご利益:開運・健康長寿・お清め
露天神社には「御井社・祓戸社」と、呼ばれる井戸があります。
今はカラカラになっているものの、かつては湧き水が出て人々の喉を潤していました。
「露天神社」の名前の由来は菅原道真が詠んだ句とは他に、井戸から出ていた湧き水が関係しているのではと見られています。
御井神は井戸の神様で、生命と幸福と清らかさを象徴。
祓戸社四柱ノ神とは、瀬織津比売(せおりつひめ)・速開都比売(はやあきつひめ)・気吹戸主(いぶきどぬし)・速佐須良比売(はやさすらひめ)の4人の神様です。
お初天神の関連記事
関連記事:![]() 【期間限定の御朱印はあるの?】露天神社(お初天神)の御朱印の種類・値段・授与場所の混雑具合をご紹介!
【期間限定の御朱印はあるの?】露天神社(お初天神)の御朱印の種類・値段・授与場所の混雑具合をご紹介!
関連記事:![]() お初天神(露天神社)にはオリジナルの御朱印帳がある!種類・値段と授与場所の受付時間など
お初天神(露天神社)にはオリジナルの御朱印帳がある!種類・値段と授与場所の受付時間など
関連記事:![]() お初天神(露天神社)のお守り一覧「種類(ご利益)・値段・授与場所・授与時間(営業時間)」をご紹介!!
お初天神(露天神社)のお守り一覧「種類(ご利益)・値段・授与場所・授与時間(営業時間)」をご紹介!!
スポンサードリンク -Sponsored Link-
当サイトの内容には一部、専門性のある掲載がありますが、これらは信頼できる情報源を複数参照して掲載しているつもりです。 また、閲覧者様に予告なく内容を変更することがありますのでご了承下さい。